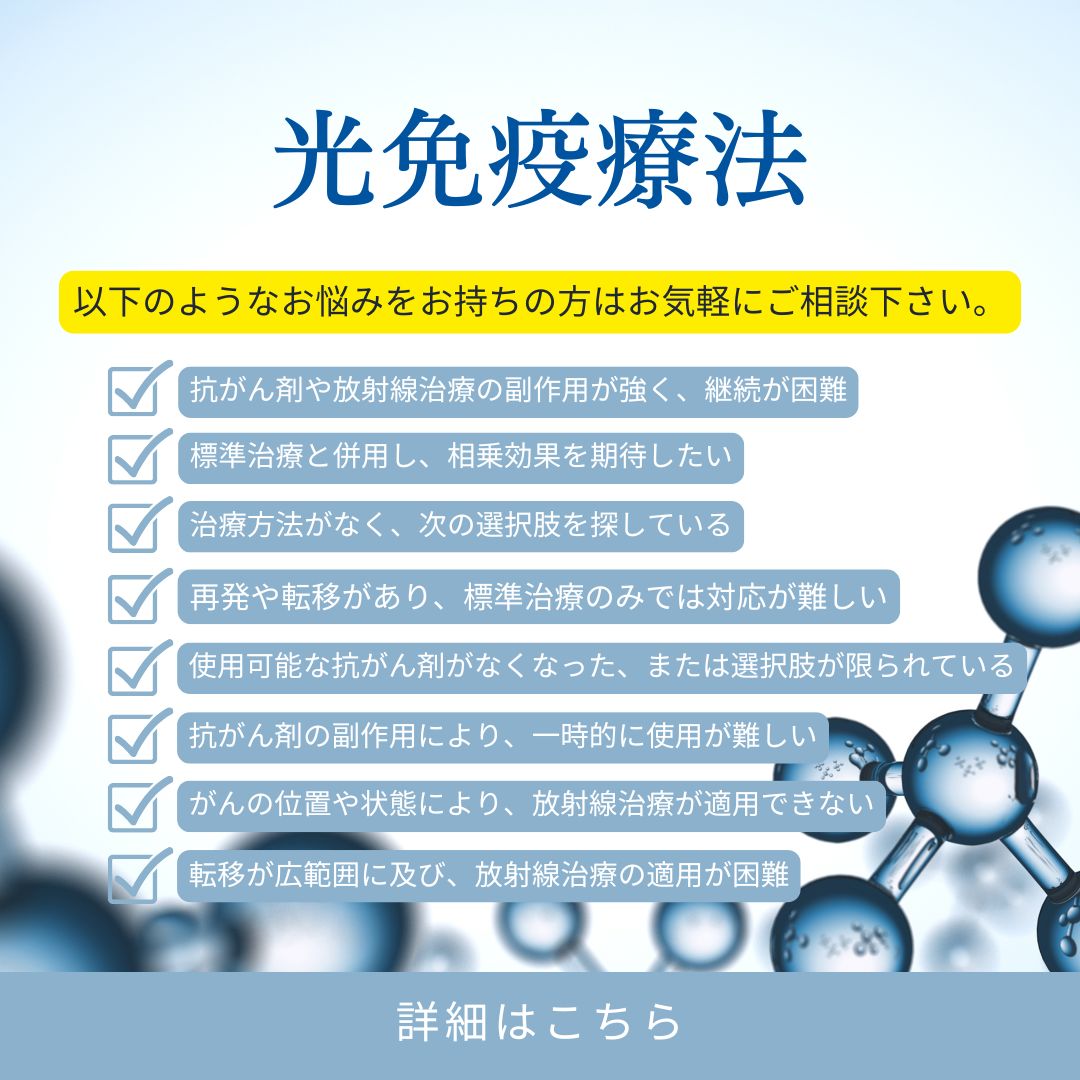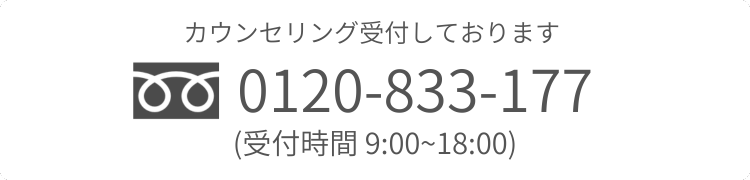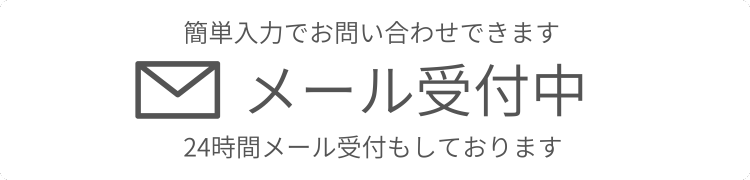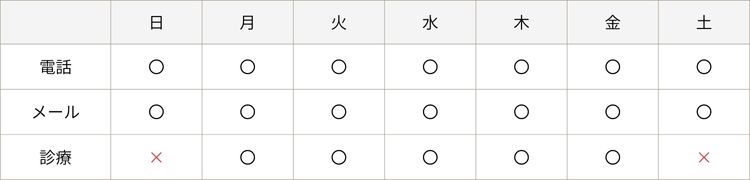がん治療は、病状や治療方法によっては長期間の入院や頻繁な通院が必要になることがあります。
しかし、仕事や家庭の事情、経済的な負担、体力的な問題などにより、長期の入院や頻回の通院が難しいと感じる患者様も多いです。
近年、がん治療の選択肢は広がっており、在宅医療、緩和ケア、通院間隔の調整、負担の少ない治療など、患者様の生活状況に応じた治療が可能になっています。
本記事では、がん治療の長期入院や頻回通院が難しい理由と、それに対応するための方法について詳しく解説します。
1. がん治療の長期入院や頻回通院が必要な理由
がんの種類や進行度、治療方法によっては、長期間の入院治療や頻繁な通院が求められます。
以下のようなケースでは、定期的な医療機関への受診が必要になります。
| 治療・管理の種類 | 内容 | 通院スケジュール |
|---|---|---|
| ① 抗がん剤治療(化学療法) |
抗がん剤は通常、数週間から数ヶ月のスケジュールで継続的に投与されます。 特に、点滴による投与が必要な場合は、頻繁に病院へ通う必要があります。 治療の進行状況や副作用の管理のため、定期的な診察や検査が必要です。 また、薬剤の種類によっては、投与スケジュールが異なるため、個々の治療計画に応じた対応が求められます。 |
|
| ② 放射線治療 |
放射線治療は、1回あたりの治療時間は短いものの、週5回×数週間にわたって継続する必要があります。 治療効果を最大限にするために、定期的に照射を行う必要があり、スケジュール管理が重要です。 また、放射線治療に伴う皮膚炎や倦怠感などの副作用の管理も必要になります。 放射線治療を行う部位によっては、追加の検査や専門医の診察が求められる場合があります。 |
|
| ③ 手術後のリハビリ・経過観察 |
がんの手術を受けた後、回復のためにリハビリや経過観察が必要になります。 特に、消化器がんや肺がんの手術後は、体力の回復に時間がかかるため、定期的なフォローアップが求められます。 また、手術後の合併症を防ぐために、感染症管理や栄養管理が重要です。 一部の手術では、人工肛門(ストーマ)や人工膀胱を装着することになり、それに伴うケア指導が必要となる場合があります。 |
|
| ④ 副作用や合併症の管理 |
がん治療には副作用が伴うため、治療中や治療後に発熱、貧血、感染症などの管理が必要になります。 特に、免疫力が低下しやすい化学療法中の患者は、感染症予防のために頻繁な通院が求められます。 また、放射線治療による皮膚障害や内臓の炎症、手術後の創部感染なども、適切な対応が必要になります。 副作用の発生リスクを抑えるために、適切な薬剤投与や栄養管理が行われることが推奨されています。 |
|
2. がん治療の長期入院や頻回通院が難しい理由
がん治療は、患者様の健康状態や治療計画によっては、週に何度も通院が必要だったり、数週間から数カ月の入院が必要になったりします。
しかし、すべての患者様がそのような治療を受けることができるわけではありません。
ここでは、がん治療の長期入院や頻回通院が難しいと感じる主な理由について詳しく説明します。
| 通院や入院が難しい理由 | 詳細 |
|---|---|
| ① 仕事や家庭の事情による負担 |
がんと診断された後も、仕事を続けながら治療を受けたいと考える患者様は少なくありません。しかし、がん治療は定期的な通院が求められることが多く、働きながら通院を続けるのは容易ではありません。
特に、放射線治療は1回あたりの治療時間は短くても、週5回の通院を4〜6週間継続する必要があるため、仕事と両立することが難しくなる場合があります。 また、家族の介護や育児をしながら治療を受ける患者様にとっても、頻繁な通院や長期入院は大きな負担となります。特に、小さな子供がいる場合や、高齢の親の介護をしている場合には、長期間家を空けることが難しく、家族の協力なしでは治療を続けるのが困難になります。 |
| ② 経済的な負担 |
がん治療は医療費だけでなく、交通費や宿泊費、食費などの間接的な費用もかかります。
特に、がん専門病院での治療を受けるために遠方から通院する患者様にとっては、長時間の移動や宿泊費の負担が大きくなることが問題となります。 さらに、治療期間中に仕事を続けることが難しくなり、収入が減少することも、経済的な不安を大きくする要因となります。収入が減ることで、治療費の負担がさらに重くなり、必要な治療を途中で諦めてしまうケースも少なくありません。 |
| ③ 体力的な問題 |
がん治療は、体への負担が大きいため、患者様の体力や免疫力が低下し、頻繁な通院が困難になることがあります。
特に、高齢の患者様や、すでにがんが進行している患者様にとって、頻回の通院は大きな負担となります。 また、化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療の副作用として、強い倦怠感や吐き気、貧血などが現れることがあり、病院への移動が困難になることもあります。 さらに、免疫力が低下している患者様にとって、病院への移動は感染症のリスクを高めることにもなり、外出そのものが危険な場合もあります。 |
| ④ 地理的要因(病院が遠い・移動が困難) |
都市部に住んでいる患者様であれば、比較的アクセスの良い病院で治療を受けることができますが、地方に住んでいる患者様にとっては、近くに適切ながん治療を受けられる医療機関がない場合があります。
そのため、専門的な治療を受けるために、何時間もかけて病院へ通院しなければならないこともあり、長期的に続けるのが難しくなります。 また、冬場の雪や悪天候の影響で通院が困難になる地域もあります。交通手段が限られている場合や、公共交通機関が利用できない場合には、通院そのものが患者様にとって大きなストレスとなります。 |
3. 長期入院や頻回通院が難しい場合の対策
長期のがん治療が困難な理由は、身体面や経済面、更に環境面といった様々な要因がありますが、ここではそれらの負担を減らすための選択肢を詳しくみていきたいと思います。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| ① 通院回数を減らす方法 |
通院回数を減らすためには、患者様の状態に応じた治療の調整が必要になります。 例えば、化学療法のスケジュールを調整することで、投与間隔を長くしたり、内服薬(飲み薬)に変更することができる場合があります。 また、放射線治療では、通常は1日1回の治療が標準的ですが、治療期間を短縮するために、1回の線量を増やし、通院回数を減らす方法(寡分割照射)を選択できる場合もあります。 通院回数を減らす方法:
|
| ② 在宅医療(訪問診療・訪問看護)の活用 |
在宅医療を活用することで、医師や看護師が自宅を訪問し、点滴や経過観察を行うことが可能になります。
在宅医療の活用方法:
|
| ③ 近隣の病院との連携 |
遠方のがん専門病院で治療を受ける場合、地元の病院と連携し、定期的なフォローアップを近隣の医療機関で行うことが可能です。
近隣病院との連携方法:
|
| ④ 治療方法の見直し |
通院が負担になりすぎる場合は、治療方針を変更することも検討できます。
治療方法の見直しの選択肢:
|
4. まとめ
今回の記事のまとめは以下の通りです。
| 項目 |
|---|
| がん治療では、化学療法・放射線治療・手術後の経過観察などで長期入院や頻回通院が必要になることが多い |
| 仕事・家庭の事情、経済的負担、体力的な問題により、通院が難しくなることがある |
| 外来治療・在宅医療・地域医療連携を活用することで、通院負担を減らすことが可能 |
| 治療法を見直し、生活の質を優先した治療を選択することも大切 |
がん治療を続けながら生活を維持するためには、自分の状況に合った治療計画を立てることが重要です。主治医と相談しながら、無理のない治療法を選択していきましょう。

【当該記事監修者】院長 小林賢次
がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。